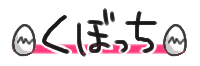
~口頭試問振り返りレポート~
第4回発表で私の論文は、「1970年から2013年までの『友達親子』や『友達のような親子関係』は雑誌でどのように語られているのか」というテーマに決まった。
(第4回発表振り返りレポートはこちらhttp://www1.meijigakuin.ac.jp/~hhsemi13/index-egg/egg-works/egg-works-frikaeri/frikaeri_kubocchi4.html )
それ以降、国会図書館や雑誌専門の図書館である大宅壮一文庫に通って、「友達のような親子関係」について述べられている記事をひたすら探して集めていた。
しかし、テーマが決定してから2週間たった時、集めた記事を見て思ったのが1990年代以前の「友達親子」という言葉が現れる前は「友達のような親子関係」
はどのような言葉で説明されているのか、また、語りの変遷を追うにも、社会状況がどういう風に変わっていったのかが分からなければ、何がキッカケで語られ方が変化をしたのかが分からないのではないか、という考えに至った。
それだと、ただの雑誌の内容を集めただけのもので終わってしまう気がした。そんなことを考えている時、語りの変遷を見ている雑誌の中の一つに『児童心理』(金子書房)という教育専門雑誌があった。
『児童心理』は発刊されている期間も長く、子供の問題について専門的に扱っている論文雑誌だ。また、『児童心理』の論文の中には社会的な背景と合わせて子供の状況を論じているものもある。
そのため「これならば社会的な語りの変遷を知識の土台として見て行くことができるのではないか、そしてこのことを踏まえて、他の雑誌に書かれている『友達のような親子関係』の語りの変遷や
1990年以前の『友達のような親子関係』がどういう言葉で説明されていたのかが分かるのではないか」と思った。そこでそれ以降は『児童心理』以外の雑誌を見るのを一旦止めて、
『児童心理』を中心に見て行こうとした。そして、『児童心理』を2013年まで見終わった後に他の雑誌を再び見ようと決めた。
しかし、私のやり方は、『児童心理』の論文ごとに内容を卒論の本文として直接まとめるのではなく、エクセルの表にまとめるという非常に効率の悪い物だった。
エクセルは表になっているため、分類のしやすさや語りの流れが一目で見やすいのではないかと思っていたのでエクセルを使ってまとめていた。
けれどもそのやり方は、エクセルに簡単に内容をまとめていただけだったので、一通りまとめ終わった後、論文を執筆する時に内容が簡素過ぎて分からない場合、また『児童心理』を見直さなければならない事態になってしまう。
そのため、長谷川先生から「<くぼっち>がそうやるのは自由だが、これでゼミ内提出日である12月25日までに終わるのか」と聞かれた。
長谷川ゼミでは、卒論の本提出日である1月8日よりも前に考察以外のすべての部分を書き上げ、長谷川ゼミのメーリングリスト上にデータを提出する。
それが私たちの代では12月25日だった。正直言って『児童心理』だけでも1970年から2013年まで見て行くのには膨大な量があり、とても終わりそうにないだろうと薄々思っていた。
ただし、これはやり方が悪いのではなく、私のやっているスピードに問題があると思っていた。そのため「時間が無いのなら、スピードを上げて頑張って終わらせるんだ」と思って、現実的なプランを立てずに、気持ちで乗り切ろうとしていたのだ。
この時、思った以上に私の状況が良くないことを先生から指摘されて初めて気が付いた。さらに、私は自分の状況を誰にも話していなかったため、ゼミ生たちも私がそんな状態になっている事を知らずにいた。
先生に「<くぼっち>のこの状況を知っていた人はいなかったのか」とゼミ生が聞かれていたのを見て、第4回発表終了時に「悩んだら手遅れになる前に相談しよう」と決めたことは、それだけでは不十分で、たとえ悩んでいなくても、どういう進行状況なのかを誰かに話す必要があると思った。
何故なら自分が思わぬ方向に進んでしまっていることに気づかずに進めてしまっている可能性もあることが解ったからだ。現状の報告をしあうことで、より良い方法を提案したり、「今やるべきことはそれじゃない」などといった軌道修正をしたりすることもできる。
そのため、それ以降は、ゼミ以外でお昼ご飯を食べる時にゼミ生に呼びかけたり、呼びかけに応じたりして現状を話し合うようになった。これを機に自分の考えが独りよがりにならなくなっただけでなく、卒論に対するプレッシャーもゼミ生と会って話すことで和らいでいったのを実感していた。
また私はこの頃、先述したこと以外にも、卒論の状況が芳しくないのに自分に危機感を持つことができず、そのことを何度も先生に注意されていた。
このままでは、再び同じことを繰り返し続け、卒論執筆にも大きな支障をきたすだろうと思った。そのため、何故自分は先生に何度指摘されても、同じことを繰り返してしまうのかについて考えた。
このことについて考えたことが私にとって大きな転換点だったと思う。それをきっかけに「自分はできる」という思い込みをしていたこと、無意識の内に自分が人に対して「甘えている」ということに気が付いた。
そして、現状の自分に甘んじていることに対して「気持ち悪さ」を覚えて、そんな状態から抜け出したいと思うようになったのだ。
その事を綴った11月25日に更新したゼミブログ(「残り1か月/さよなら優等生」http://hajime-semi.jugem.jp/?eid=373 ) について、先生から「<くぼっち>のブログが良かった。
貴女はそうやって考えることができるのだから、卒論だってやればできる。自分の精一杯を出し切りなさい」と言って頂いた。まさか褒められると思っていなかった。
今まで自分が「誰かに褒められるために」何でもやってきて、「そういう考えの元で振る舞った成果から褒められたこと」とは違った感覚で、先生の言葉を受け止めている自分がいた。
初めて「褒められたいから頑張ろう」ではなく「私だってやればできるんだから頑張ろう」と思って卒論に取り組んでいた。つまり、初めて「誰かに認められるために」ではなく、他ならぬ「自分自身のために」頑張ろうとしていたのだ。
この頃は『児童心理』の膨大な量と卒論仮提出までの残り時間を考えて『児童心理』以外の雑誌をあたることは諦めることにした。卒論のタイトルも「『友達みたいな親子関係』は、いかに語られてきたのか――『児童心理』1970-2013を読む」というものに決定した。
しかし、『児童心理』の中からだけでも何か得られれば、と1970年から2013年までの「友達のような親子関係」に関する論文を必死になって読み漁っていた。
「友達のような親子関係」に関する論文を執筆して解ったことが二つあった。一つは『児童心理』に書かれていたことを通じて見た「友達親子」に関する語りが、自分と家族の関係とそっくりであったことだ。
特に母親と子供が心理的な距離が非常に近い状態である「母子癒着」はまさに私と自分の母親の関係そのものだと思った。私は第4回の発表の時点では自分が「母子癒着」状態であるなどと微塵もおもっていなかったため、論文執筆を通じて自分の状況を捉え直すことができたのだ。
自分でも気づかぬうちに現代親子の1つの形を体現していること、そして、先述したブログの内容も関連して、自分がいかに精神的に子供で自立できていないかを思い知らされた。
もう一つは論文を執筆していて、自分の持っている知識が、ほぼ空っぽであるがために「論じる」という事ができないということだった。
何回読み直しても「『児童心理』に書かれている事が、私の家族の状況と似ている」「『友達親子』は学者の間ではあまり肯定的な意味合いでは使用されていないんだな」といった感想しか出てこなかった。
そして、誰かの意見を代弁してそのまま事実として述べているだけで、自分の客観的な考えがなさすぎる自分の論文を「つまらない」と思った。今まで「友達親子」に関する文献をテーマ決定までの段階でもっと読んでいれば良かったと後悔してもどうしようもなかった。
卒論本提出である1月8日までに自分にできることを考えて最後まで粘ったものの、思い浮かんだ「自分にできること」が限られており「今の私にはこれしかできないのだ」と痛感した。
何とか論文の文字数や註・付録など、学校で指定されていた規定を満たした状態で卒論を無事提出し終えても、達成感やすっきりした感じは私の中には無かった。
上手く説明できないモヤモヤしたものが残っていた。しかし、書き上げた論文に今の自分のやれる事の全てを詰め込んだため「これが今の私なんだな」と受け止めようと思っていた。
ところが、口頭試問の準備の時、再びダメな自分を突き付けられることになった。口頭試問で読み上げる原稿を作成するために、改めて自分の論文を読み直した時に、誤字を発見した。
あれだけ細心の注意を払っていたにも関わらず、気が付かなかったことにショックを受けていた。また、発表原稿の読み合せをしていた時に<あっこ>から
「<くぼっち>の文章は、読んだ時に解りやすく書かれているんだと思うけど、内容を聞いているだけだとどこが大事なのか解らない」という指摘を貰った。
自分で読んでいて、自分の論文が「つまらない」と思った理由の原因はここにもあると思った。私は、『児童心理』で得た内容の全部が大事だと思ってしまい、
「友達のような親子関係」の語りの変遷において本当に抑えるべきポイントを上手くまとめられていなかったのだ。口頭試問の原稿は自分の論文の要約に等しいため、それは論文の中身にも言えるだろうと思った。
家で「聞いて解りやすい発表」にしようと何度も声を出して読みながら原稿を修正している際、私は泣いていた。
「書き上げた論文=今の自分」だということは「私は、自分の意見が無く、どこがポイントなのかも分からないような、つまらないことしか言えません」と自分の論文を通じて言っているのだという事実に耐えられなかった。
結局、卒論を提出した時点ではまだ自分のことを受け入れられていなかったのだ。1月8日の卒論提出時に感じた説明のできないモヤモヤした感覚は、多分これだったのかもしれない。
口頭試問本番でも泣かないように意識していたものの、結局発表の途中で涙が出てしまった。やはり、悔しかったのだ。
しかし、ゼミ生や先生や、次の年の長谷川ゼミ生である3年生が自分の発表を聞いていると考えたら、「そう、これが今の私なんだよ!」と思い始めて、教室にいる全員に聞こえるような声で原稿を読んでいた。
そして、読み終えた時、まだ泣いてはいたが、心がすっきりしていた。後に<サラダ>から聞いた話では「<くぼっち>はなんだか吹っ切れたみたいだった」ということだった。
親に甘えて自立ができていない、そして、「自分の意見が無く、どこがポイントなのかも分からないような、つまらないことしか言えない」という「今の私」を受け入れられたのかもしれない。
その証拠に、先生からの質問に答えている時に、「私また泣いてる、なんで泣いてるんだろう」と思ったら、自分の泣いている状態が、非常に愉快になって、突然笑い出してしまった。
端から見たら、泣きながら笑っているのだからとても不気味だったと思う。
先生からは「卒論執筆の最後の方でチャレンジした。一歩踏み出した」という言葉を頂いた。先生の言うチャレンジとは、「何かを掴み取るために自分を賭けること」だ。
私は、自分が甘えているという状態に気が付いた時、「今まで泥臭い努力」をしてこなかったとブログで振り返っている。その泥臭い努力をしてみようと一念発起して卒論に取り組んだことが、
私にとってチャレンジだったのかもしれない。私の論文自体、できは良くなかったため、口頭試問ではあまり良い評価をされないだろうと思っていたので先生からの言葉には驚いた。
しかし、結果には繋がらなかったものの、ゼミに入った当時と比べたら自分のことが解るようになったというのは確かな変化だった。それは、きっとチャレンジした結果なのだ。
自分の事は自分が一番解っている、というのは驕りなのかもしれないと今は思う。長谷川ゼミを通してこのことに気が付かないまま社会に出ていたらと思うと恐ろしい。
そして先生からは、この論文が私のチャレンジのスタート地点だということ。また、論文執筆についての反省の中に「時間配分のミス」を挙げていたが、その考えは良くない、そういう考えは逃げだ、という話もされた。
考察がしっかりとできた客観的な論文を完成させるために「やるべきこと」を、やりたくなかったから、やらなかったのであり、「時間配分のミス」は体の良い言い訳に過ぎないのだ。
自分の状態に気が付けてもまだまだ言い訳癖が抜けていないなと思った。言い訳をして自分を守って本当に向き合わなければならないことをやってこなかった、即ち逃げたから、結果的に自分の論文の出来が良くなかったのだ。
「やるべきこと」をやらなかったのだから、結果に繋がらないのは当然のことだ。今後「時間配分のミスではなく逃げである」ということは絶対に忘れないようにしようと心に刻んだ。
こうして、卒論を通じて自分の今後の課題を見つけることができた。卒論を提出して「あー良かった、これで終わり」としてしまうのは非常にもったいない。
そんな風に思っていた口頭試問の打ち上げの時に、2009年度長谷川ゼミ生の<ヤダ>さんと、2010年度長谷川ゼミ生の<ふーみん>さんから、
長谷川ゼミの卒業生同士でゼミのような勉強会を、仕事をしながら行なっているという話を聞いた。「もっと勉強をしたい」と思っていた私には、とても魅力的な話に思え、興味が湧いた。
まだ就活が終わっていないため4月以降どうなるのかが分からない。しかし、是非参加したいという旨を2人に伝えた。
卒論を通じて掴んだものを生かすも殺すも、今後の私の行動にかかっている。「なんで?と周囲の出来事に疑問を持つこと」「率直になって色んな人に話を聞いてもらうこと」
「言い訳をして逃げないこと」「沢山の本を読んで教養を身につけること」そして「ダメな自分を受け入れること」。これらが今後の私の行動の指標となっていくと思う。